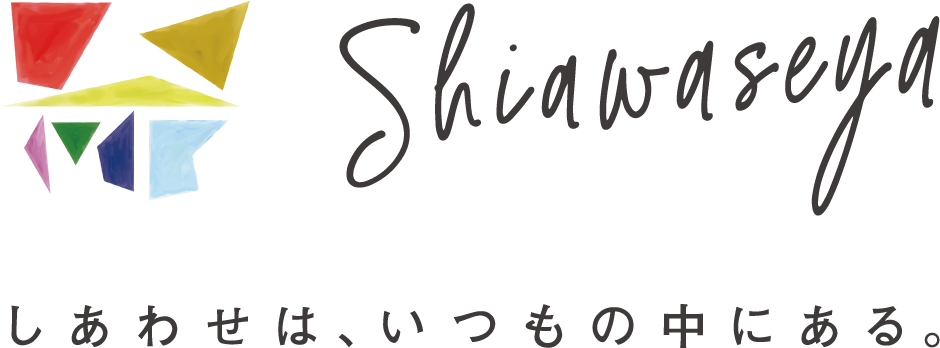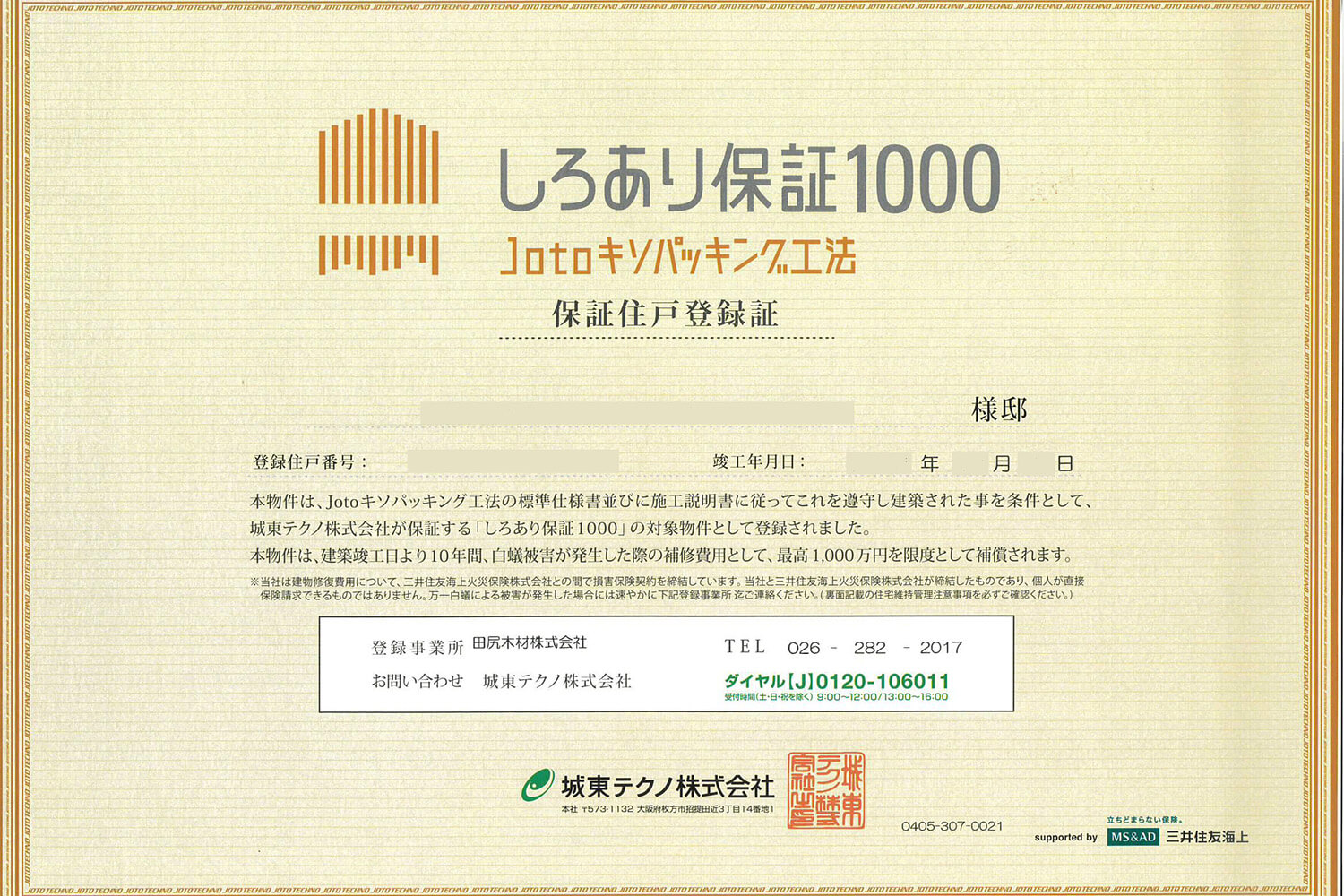<気密断熱の話> 断熱について Ua値 2階建0.41 平屋0.34
これから永く快適に暮らしていただくために、冬暖かく、夏涼しい、結露や経年劣化に強いグラスウールのブローイング式断熱工法を中心に採用。グラスウールは住宅用断熱材として約40%という圧倒的シェアを占め、原料の80%以上が家庭などから回収されるガラス素材のリサイクルでつくられており、断熱材の中でも製造時に地球環境に与える負荷が極めて低い素材です。さらに高い防音効果を持ち、コストパフォーマンスに優れた優秀な断熱材です。弊社はこの断熱材を壁に100ミリ(実質105ミリ)、天井には300ミリとふんだんに使用、平均的な2階建ての間取りで外皮性能Ua値=0.41~0.45、平屋の間取りではUA値=0.34~0.38となっています。この値は長野市エリアでのZEH基準(Ua値=0.60)を大きく上回る性能となっています。またそれを上回るご要望にも積極的に対応しております。具体的には「付加断熱」と呼ばれる手法で断熱性能を増すのですが、2015年に建築した弊社社屋は、その時点で付加断熱を施して建築しています。
※注(株)矢野経済研究所調べ2020年度